
『明日に向かって撃て!』 悲劇前、自転車に乗る軽やかな時間
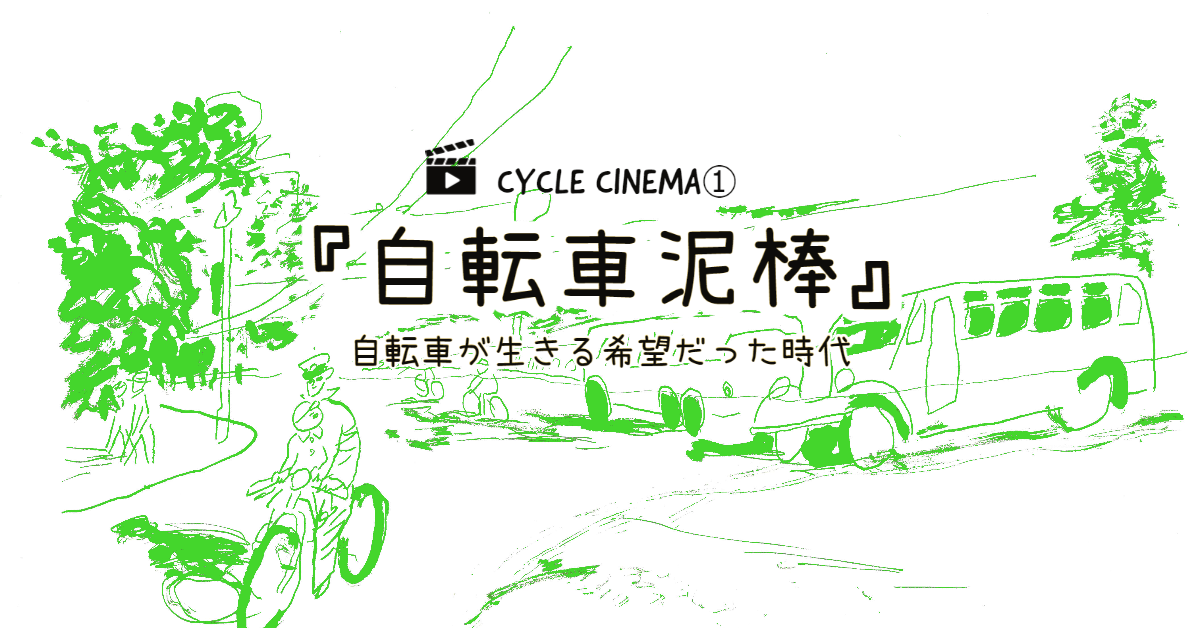
自転車の盗難。誰しも、この最悪の事態を避けたいだろう。パーツやボディの素材を厳選し、1グラム単位で重量を削減するのに、盗難対策のチェーンロックが500グラムもするなんて本末転倒もいいところだ。許すまじ自転車泥棒。この世からいなくなって欲しい。
『自転車泥棒』(1948年)という古い映画がある。監督はヴィットリオ・デ・シーカ(ウクライナのひまわり畑で撮影した『ひまわり』が有名)。本作は戦後のイタリアの労働者を描いた切ない映画だ。
舞台は第二次世界大戦後のローマ。戦後の不況は深刻で主人公のアントニオは2年も仕事に就けていない。このままでは家族が餓えてしまう。職業安定所の紹介でポスター貼りの仕事を見つけるが、ひとつの条件があった。自転車が必要だという。彼の自転車は質に入れており、家族の協力でなんとか取り戻すことができた。自転車に仕事道具を積み込み、意気揚々と仕事に向かうアントニオ。これで生活は少しずつ良くなるはずだ。希望が見えてきたのも束の間、初日に自転車を盗まれてしまう(なにやってんだよ)。自転車を失うということは、仕事を失ってしまうということだ。息子と共に町中を探すが自転車は出てこない。
マンマ・ミーア! 途方に暮れるアントニオ。
失意のどん底、鍵のない自転車を見つけるアントニオ。
自転車さえあれば仕事ができるぞアントニオ。
悪魔の誘惑に勝てず、アントニオは罪を犯してしまう。誰が彼の罪を責められよう。が、自転車の持ち主はアントニオの都合なんて知るわけもない。哀れアントニオは息子の前でボッコボコにされてしまうのだ。
不思議なことに、映画を観ると罪を犯した男を切なく思い、応援していることに気づく。自転車泥棒、あんなに許しがたい存在なのに。自転車を愛する人たちはこの映画を観てどう感じるか。ぜひ、ご自身で確認して欲しい。

🎬CYCLE CINEMA STORAGE🎬
#01 “自転車泥棒”
#02 “プロジェクトA”
#03 “明日に向かって撃て!”
#04 “少年と自転車”
#05 “居酒屋兆治”
#06 “ニュー・シネマ・パラダイス”
#07 “キッズ リターン”
#08 “PERFECT DAYS”
#09 “クレイマー、クレイマー”
#10 “E.T.”
#11 “ガチ星”
#12 “イエスタデイ”
#13 “少女は自転車にのって”
#14 “関心領域”
#15 “アンゼルム”
#16 “男はつらいよ”
Text_井上英樹/Hideki Inoue
兵庫県尼崎市出身。ライター、編集者。趣味は温浴とスキーと釣り。縁はないけど勝手に滋賀県研究を行っている。1カ所に留まる釣りではなく、積極的に足を使って移動する釣りのスタイル「ランガン」(RUN&GUN)が好み。このスタイルに自転車を用いようと、自転車を運搬する為に車を購入する予定(本末転倒)。
投稿日:2023.07.21